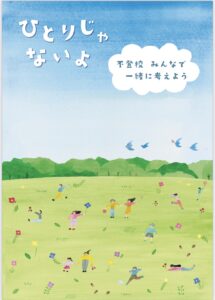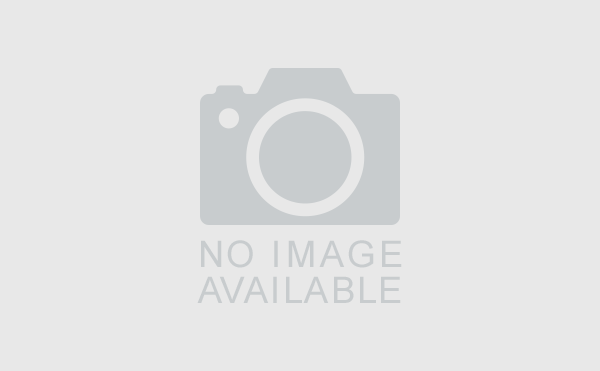2025年3月議会一般質問② 「主権者教育を進め、こどもの声を施策につなげよう」
2件目の質問
「主権者教育を進め、こどもの声を施策につなげよう」
2024年10月に行われた衆議院議員選挙での、18,19歳の投票率は、43.06%でした。また文部科学省の「我が国と諸外国のこどもと若者の意識に関する調査」の報告で、「私の参加により変えてほしい社会現象が変えられるかもしれない」の問いに肯定的な回答をした日本の若者は36%で、他国に比べて一番低い結果でした。
一方、幼いころからあらゆる場面で社会参画が保障されているスウェーデンでの、第二次世界大戦後から2002年までの若者の平均投票率は87%です。
主権者教育をどう進めているのか
市からは、自ら考え、判断し、行動していく力を養う教育であると捉え、選挙権を持つ前の段階から継続的に主権者教育を進めていくことが必要との答弁がありました。
現在、小・中学校で行っている模擬投票では、どんな学校にしたいかや給食などについて取り上げるなど、身近な課題を取り上げているとのことです。
盛岡市の高校で行われた、政党の政策を実際の議員から聞いた後に模擬投票を行った例を紹介し、小平市でも実施できるのではないかと提案しました。
学校生活の環境整備でも、子どもの声を聴くべき
校則や制服の変更については、子どもたちの意見を聴きながら行っているとのことです。しかしながら、子どもからは、何かしら不満の声が聞こえてきます。家庭で愚痴を言うのではなく、学校生活の中で意見を聴く時間を設け、過ごしやすい環境づくりに自分の声を聴いてもらえるという体験が主権者教育につながるので、そのような体制づくりを求めました。
また、昨年から始まった特別活動の日の児童会・生徒会サミットについては、参加している実感がないとの子どもの声を聴いています。昨年度は、より良い学校にするにはということで話し合われ、今年は地域に広げて行っていくとのことです。取組の意義を理解すること、活動が積み重なっていくこと、そして子どもが主体となって行っていける活動にしていくことを要望しました。
「こども計画」は子どもの声を聴いて
小平市で策定を進めている「こども計画」の中に子どもの意見聴取とその声を施策に反映すること、参加の保障を盛込み、子どもの権利の認識を深めることなどを要望し、小平市として主権者教育を進めていくことを求めました。