一般質問報告その2 オストメイトの災害時の備えについて
 大腸がんや膀胱がんなどの病気や事故等が原因でストーマ(排泄口)をお腹に造設して、装具を装着して排泄物をため処理をするオストメイトは、小平市内に概ね242人(2023年にストーマ装具の補助金申請があった人数)います。外見からはわかりにくいことから、配慮の必要性が十分に周知されていませんが、災害時には、オストメイト対応トイレやストーマ装具の装着や交換の場所の確保、排泄に必要なストーマ装具等の入手など様々な備えが必要です。
大腸がんや膀胱がんなどの病気や事故等が原因でストーマ(排泄口)をお腹に造設して、装具を装着して排泄物をため処理をするオストメイトは、小平市内に概ね242人(2023年にストーマ装具の補助金申請があった人数)います。外見からはわかりにくいことから、配慮の必要性が十分に周知されていませんが、災害時には、オストメイト対応トイレやストーマ装具の装着や交換の場所の確保、排泄に必要なストーマ装具等の入手など様々な備えが必要です。
今回の質問で、福祉避難所となる市内19か所の地域センターに組み立て式のオストメイト対応トイレを備蓄していることを確認できました。一次避難所では、小学校9校、中学校2校にはオストメイト対応トイレが設置されているほか、多目的トイレも利用できるとのこと。また、本年度購入予定のトイレトラックにも対応のトイレの設備があるとのことでした。ストーマ装具の備蓄はなく、装具を入手するための販売店との協定もしておらず必要な支援がまだ足りないことがわかり、対応が必要と感じました。
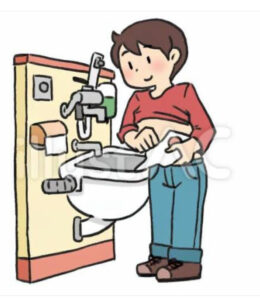 オストメイトは、それぞれが自分に合ったストーマ装具を使用しています。そのため災害時にストーマ装具を持ち出せなかったことを想定して、離れて暮らす家族や友人に預かってもらい必要な時に入手するための分散保管を行っています。立川市や町田市は、この分散保管の場所(公共施設)を提供しています。また、災害時にストーマ装具の無料提供を行っている日本オストミー協会は、自分が使用する装具の情報等を記載するオストメイトカードを作成し携帯することを紹介しています。分散保管をする場所の提供については、研究していくとの答弁にとどまりましたが、日本オストメイト協会などの支援団体の周知やオストメイトカードの紹介についてはPR できる機会を設けていくとの答弁でした。
オストメイトは、それぞれが自分に合ったストーマ装具を使用しています。そのため災害時にストーマ装具を持ち出せなかったことを想定して、離れて暮らす家族や友人に預かってもらい必要な時に入手するための分散保管を行っています。立川市や町田市は、この分散保管の場所(公共施設)を提供しています。また、災害時にストーマ装具の無料提供を行っている日本オストミー協会は、自分が使用する装具の情報等を記載するオストメイトカードを作成し携帯することを紹介しています。分散保管をする場所の提供については、研究していくとの答弁にとどまりましたが、日本オストメイト協会などの支援団体の周知やオストメイトカードの紹介についてはPR できる機会を設けていくとの答弁でした。
福祉避難所マニュアルを作成の際には、マニュアル作成のためのガイドラインだけに頼らず、オストメイトをはじめ個々の障がいに対する配慮について当事者の声を聴き、作成してくことが必要です。生活者ネットは、丁寧にその声に耳を傾け必要な施策を提案していきます。

